|
PIRKA SIRI ◆◆◆ |
||||||
|
|
||||||
●1/アイヌ民族とは? 「アイヌ民族」を大きく(つまりいいかげんに…学者じゃないもんで…)捉えると、「狩猟・漁労・採集を主に生業とし、生活地域によっては大陸などと貿易もしつつ、青森・秋田・岩手あたりの以北より北方四島あたり以南を中心に生活していた日本の先住民族である」といえましょうか。 「アイヌ民族」を大きく(つまりいいかげんに…学者じゃないもんで…)捉えると、「狩猟・漁労・採集を主に生業とし、生活地域によっては大陸などと貿易もしつつ、青森・秋田・岩手あたりの以北より北方四島あたり以南を中心に生活していた日本の先住民族である」といえましょうか。縄文時代より縄文文化を敬承しつつあるころ、弥生〜古墳時代にヤマト政権により日本周辺(北と南)に移動したのがアイヌ民族と琉球民族の祖ではないか?とシロート考えで思っていますが、その後、オホーツク文化や擦文文化とも融合しつつ「アイヌ文化」として確立されていったようです。 歴史的にみると、アイヌ民族が有する文化として、いわゆる「アイヌ文化」というスタイルが形づくられた(という表現は不適切かもしれませんが)のは、西暦1300年の中期ごろと思われているようです。というよりもそれ以前の記録がないのではっきりしない、というのが正直なところのようです。そして、そのころの本州以南の「和人」は鎌倉時代から室町時代へと移行する時期でした  ニュージーランドの先住民族「マオリ族」もそうですが、アイヌ民族もまた、文字を持たない民族でした。これは文化として遅れているということではなく、逆に言えば優れた「口頭伝承文化」を有していたといえるでしょう。イオマンテなどの祭りのときには、4日も続くような大長篇の伝承物語も語られたといわれています。あるお婆さんは300近くの昔話を語ることも出来たそうです。そしてなによりも、14世紀より近代にいたるまで、アイヌの文化が連綿と続いてきたことがその証拠といえるのではないでしょうか。 ニュージーランドの先住民族「マオリ族」もそうですが、アイヌ民族もまた、文字を持たない民族でした。これは文化として遅れているということではなく、逆に言えば優れた「口頭伝承文化」を有していたといえるでしょう。イオマンテなどの祭りのときには、4日も続くような大長篇の伝承物語も語られたといわれています。あるお婆さんは300近くの昔話を語ることも出来たそうです。そしてなによりも、14世紀より近代にいたるまで、アイヌの文化が連綿と続いてきたことがその証拠といえるのではないでしょうか。狩猟・漁労・採集を主に、と書きましたが、アイヌ民族は、中国やロシアあたりの内陸部や、黒龍江(アムール河)中流域などにまで交易の手を拡げていたと考えられています。そこで交換した貴族の盛装の服などを、さらに和人と食料や漆器などと交換していたようです。ちなみに漆器は宝物として扱っていて、祭や儀式のときに使用していました。 念の為、もちろん、現在ではいわゆる「日本人」と同じ暮らし方をして生活しています。同じ服を着て、同じように仕事をし、残業(^◇^)もして、税金も納めて生活しているのです。 この「アイヌの森/ピリカ・シリ」では、日本人として「同化」させられる以前、あるいは混在期(今も、かもしれませんが)のアイヌ民族の暮らしなどを中心に記していきます。 ●2/アイヌ民族の家 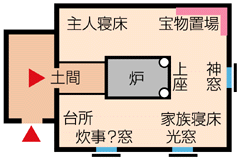 アイヌ民族の家に関しては、ここでは一般的と思われる事柄を記すことにします。 アイヌ民族の家に関しては、ここでは一般的と思われる事柄を記すことにします。「チセ」と呼ばれるアイヌ民族の家は、住む地域や環境によって素材が変わっていました。笹・草・萱・葦・樹皮などを、壁や屋根に使用し、葡萄の蔓や樹皮などで固定したようです。外観は寄せ棟造りで、支柱などは栗・桂・イヌエンジュなどを使用し、土台を置かずに地面に直接埋められて固定されていたそうです。 チセは、大きな家でも長辺9〜11m、短辺4〜6m程度だったそうです。またチセには入り口に付属する形で物置(セムと言います)がありました。ですから、一度玄関(物置)を通り、右に曲がってチセに入る、というスタイルでした。 チセには(地方によって変わりますが)3つの窓があり、入り口から一番奥の窓が儀式などに使われる窓「神窓=ロルンプヤル(カムイプヤル)」があり、次いで右側の奥に採光用の窓「イトムンプヤル」、一番手前に炊事などに使用した窓「ポンプヤル」がありました。 炉より奥(上図では上座と書いてあるあたりより右)は神(カムイ)が神窓から出入りする神聖な場所として扱われていました。こちらに足を向けて寝ることは禁じられていたそうです。 チセの左手奥には交易などで手にいれた宝物や、儀式などに使う道具などを置く場所を設けていました。  家の中心には炉が切られていて、火を絶やすことはなく、そこで煮炊きをし、暖をとり、儀式を執り行いました。アイヌにとって火は重要な存在(このあたりのお話はまいずれ)でした。また、壁面に内側から蒲(ガマ)を編んだもので囲うようにしていたので、炉の炎+壁面の断熱効果と輻射熱のおかげで真冬でも暖かく生活できました。その昔、日本式の家屋をアイヌ民族に提供したところ、彼等は寒くて生活できず、しばらくするとその家のそばにチセを建て、日本式の家は物置きとして使っていた、という話もあります 家の中心には炉が切られていて、火を絶やすことはなく、そこで煮炊きをし、暖をとり、儀式を執り行いました。アイヌにとって火は重要な存在(このあたりのお話はまいずれ)でした。また、壁面に内側から蒲(ガマ)を編んだもので囲うようにしていたので、炉の炎+壁面の断熱効果と輻射熱のおかげで真冬でも暖かく生活できました。その昔、日本式の家屋をアイヌ民族に提供したところ、彼等は寒くて生活できず、しばらくするとその家のそばにチセを建て、日本式の家は物置きとして使っていた、という話もありますチセは建てられる際に向きが決められていました。地方性がありますが、チセの中心から神窓が東に向いていたり、西に向いていたりしました。ですから、集落(コタンといいます)単位でチセの建っている向きは同じ方向を向いていました。 ●3/アイヌ民族の文様 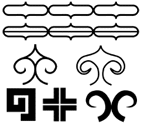 左にアイヌ民族の代表的な文様の形を書いてみました。上の横長のものが「アイウシ文」、一番下の中央にある十字のものが「ウタサ文」、その他は「モレウ文」と呼ばれるものです。 左にアイヌ民族の代表的な文様の形を書いてみました。上の横長のものが「アイウシ文」、一番下の中央にある十字のものが「ウタサ文」、その他は「モレウ文」と呼ばれるものです。これらの文様は、もっぱら刺繍で施されたようです。衣服の上に模様がでるように別の布(黒や紺や白などの木綿の布)を充て、さらにその上に刺繍で模様をつけました。刺繍はチェーンステッチやコードステッチが多いようです。ちなみに衣服の上に別の布を充てて文様を象ったものを「切伏文様」といいます。 昔は文様の形などで地方性がみられ、服を見るだけでどこの出身のアイヌか知ることができたそうです。また、切伏文様に使う布の量も地域差があり、静内地方の切伏は豊富に木綿布が手に入ったため、大胆に伏せられた文様が多くみられるとのことです。 そして現在は、伝統的な「アイウシ文」や「モレウ文」などの文様も受け継ぎながら、現代的で独創性もある文様も取り入れられて、刺繍に使う糸もカラフルになり、色鮮やかでデザイン的にも素晴らしいものが沢山作られるようになっています。 刺繍や文様は見た目の美しさだけではなく、ちゃんと意味がこめられていました。右の写真では部分的にしか確認することができませんが、刺繍は主に袖ぐちや襟首、裾廻りなどに施されています。これは、刺繍にお守りの意味が込められていて、悪神(ウェンカムイと言います)が、そうした袖ぐちや襟首、裾廻りなどの肌の出ているところから身体の中に入り込むのを防ぐように、と願って仕立てられていました。上記の文様のパターンで、どこかがとがった形をしているのはそのためです。  右の写真は白老の「アイヌ民族博物館」でのひとコマですが、昔のアイヌは、ふだんは樹皮や草などの繊維質を利用して作られた服を着ていました。このような刺繍や文様の入った服を着るのは儀式などの正装として使用したようです。 また、男性(右から2人め)も女性も同じように刺繍や文様の入った服を着ていますが、衣服に男女の区別は特になかったらしく、男性(家主?)の着るものには女性(妻?)がふんだんに文様を施して儀式などに送りだしたそうです。 ◆PHOTO CAPTION 上から〜 ●オンネトーから見た雌阿寒岳と阿寒富士 この日は少々風が強く、残念ながらオンネトーの美しさが今ひとつ出せませんでした。腕の悪さもありますが…。天気自体は上々でした。95年7月撮影 ●美幌峠から見た屈斜色路湖 私が阿寒方面に出かけて悪天候になったことはほとんどないのですね!さすがに10月に入ったときは寒かったですが。美幌峠には一昨年?までアイヌのエカシ(長老)がいました。今はたぶんいないと思いますが、このあいだテレビの旅番組にチラッとでてましたが、それは阿寒コタン(集落)での映像でした。97年10月撮影 ●クッシャロコタンのチセ 美幌峠から摩周湖方面へ向かい、屈斜路湖沿いに走るつもりで左折するとクッシャロコタンに出ます。そこにある大きなチセがこれです。中はお土産が見られるようになっています。フチ(おばあさん)がおみえになります。こちらでマタンプシ(はちまき)を買いました。雪がない間だけの営業です。97年10月撮影 ●白老のアイヌ舞踊 奥に写っているチセに雪が積もっていますね。このときは札幌にいた(当時)友人に無理を言って白老まで連れてきてもらいました。今は舞踊も屋内で演じられていると思いますが、このころはまだ冬でも屋外で行われていました。敷地のすぐ横にはポロト湖という湖があり、なんだか町のイベント(少年サッカー大会だったか?)があったようで、甘酒や豚汁が振る舞われていました。もちろん御相伴に預かりました!96年2月撮影 |
||||||
|
管理棟へメール ranger@allforest.jp 管理人・フリイ行き |
||||||